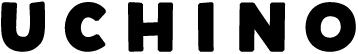
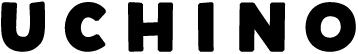

── UCHINOの契約農家になっていただいた経緯をお聞かせください。
まず、UCHINOの活動に関しては非常に素晴らしい活動だと思います!福利厚生でお米が支給される事により衣食住の食への不安が緩和され、従業員の食をも守る活動であること。また、従業員の中にはお米に困っていない方もいますが、そのお米を子ども食堂などへ独自の制度を通じて寄付することで、慈善事業としても取り組める社会的にも意義のある活動だと感じています。
自身も数年前から同じような考えを持っていましたが、1農家では限りがあり、活動としては未達になると考えました。UCHINOに参加する事により、思いの実現がより速やか、かつ持続可能になると考えたため契約農家になることを決めました。
── 「同じような考えを持っていた」、その点はどういった点でしょうか?
元々、子ども食堂へお米を提供したいとは考えていました。しかし表現は難しいですが、農家がちゃんとした寄付先を選別するのは非常に難しいことです。
UCHINOへ参加し、自身の生産したお米がUCHINO独自の”返納米制度”を通じて、子ども食堂や必要とする機関へ届いていることを非常に嬉しく思います。”返納米制度”がある事により、従業員が食べきれないお米は破棄するのではなく、社会的弱者や必要としている機関へと寄付されるので、今後より必要とされる仕組みだと思います。
── 農家の現状と今後の課題をお聞かせください。
米農家として現状困っている点は人員不足、機械の更新や選定です。今後農家の課題となってくることは、2030年問題や農業環境、農地を維持する為の農政方針であると考えます。
── 人員不足というと、昨今農家の廃業や倒産が増加傾向となっていることも問題となっていますが、その点はどうでしょうか?
割合を正確に把握している訳では無いですが、2030年には農家の数は現在の半数以下になると試算されています。農家の収入が不安定な為、後継者を育てるのではなく廃業を選択する農家が多いです。
法人化して若手農家を獲得しているところもありますが、後継者を作るのが第1目標ではなく、単純に若い動ける労働力を獲得したいように見えています。結果的に引退が近くなったタイミングで、後継者扱いへと変化をするケースが多く感じています。
── UCHINOでは契約農家へ前払い制で報酬を支払うことで、農家の安定した収入を支援する仕組みを整えています。この仕組みは具体的にどう影響しましたか?
UCHINOと契約する事により経済的安定が見込め、今後の農業事業の安定が見込めるようになりました。
現在新潟県では、1俵あたりの生産コストが20,000円程かかっており、令和5年産までの価格帯であれば1俵あたり3,000〜5,000円の赤字となります。農家が販売価格を決められるのは B to C のみであり、その B to C も市場価格の影響が大きく農家の思惑通りに販売するのは難しいです。売買の価格を提示され、その金額通り販売するのが農家なので、コスト割れを受け入れている農家が大多数です。“米は安くて当然”という考えの影響により、正確な価格を提示できず、継続や事業承継を諦める農家が大多数です。
UCHINOのような仕組みが普及し、より多くの農家に安定収入が見込めるようになれば、しっかりと後継者を獲得したい農家も増えると思います。
── 消費者や業者に求めていること、伝えたいことはありますか?
業者に対しては、2〜3年前までのコスト割れをするような価格での買取はしないで欲しいということ。消費者に対しては、2024年から米が高くなっていますが、以前の価格帯ではコスト割れをしている農家もたくさんいるという事を理解して欲しいということです。
農業はあまり目立たない分野の職業であり、農家が意見や意思を発信する機会は少ないです。食べる物は安くなければいけないという考えは間違っていて、何より安定価格かつ安定供給が重要な事を理解して欲しいです。また農業の現実や食の背景を言葉だけで伝えるのは難しいので、実際に体験をしに来ていただき現場感を伝えたいです。
UCHINOと連携して実施する農業体験では、お米を含め農産物がどのように生産されているかを言葉だけではなく体験として消費者へ伝えることができます。今後も是非参加、協力していきたいと考えています。